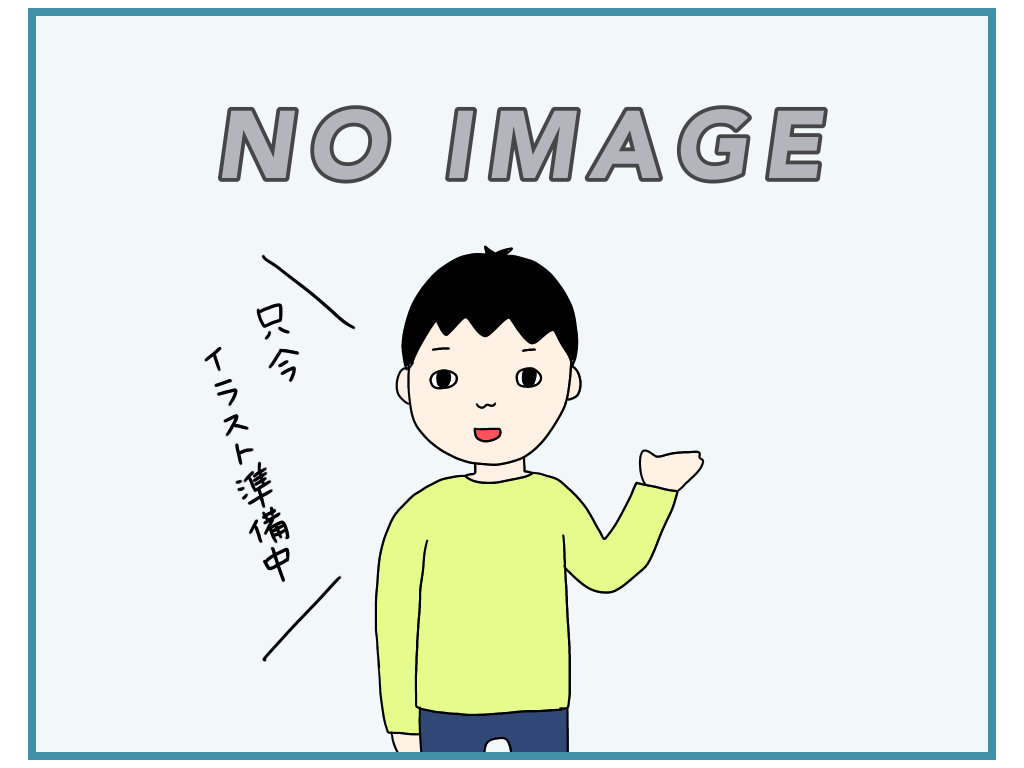これまで多くの上司と仕事をしてきました。当然、良い上司も悪い上司もいます。好きな上司もいれば嫌いな上司もいました。仕事のできる上司と仕事のできない上司に分けることもできます。
どのような角度から定義するのか難しいところですね。
しかし、学生時代のアルバイトからの仕事経験によれば間違いなく上司によって職場の生産性は大きく変化します。
アルバイト時代も店長や社員が変更となり職場の雰囲気や店舗の活気や業績が大きく変わる場面を見てきました。学生の部活動も同じで顧問や監督が変わることで大きく変わります。
アルバイトも部活も仕事もプロスポーツも全ては人間関係になります。人と人なので正解のパターンは数多くあるので難しいです。
ビジネス書を読んでも著者の一例に過ぎませんからね。どんなに努力をしても成功の可能性を100%にすることはできません。
しかし、失敗のパターンはある程度決まっていますので失敗の確率を下げることはできます。
上司が仕事の指示する目的はひとつだけ
上司の仕事の目的は部署に課せられた問題を解決することです。
医事課であれば受付とレセプトでしょう。適切な接遇と診療報酬の知識。接遇を良くするための手段として身なりを整えたり会話法を学んだりします。
医事課の上司は受付とレセプトの責任を負わされているので課題をクリアするために指示をします。
一見意味のないような指示も教育のためだったりします。
逆に言えば上司の指示というのはそれだけ責任が重いということになります。
職場が機能不全に陥っているのは上司の責任である
多くの職場では組織図があります。部長、課長、係長、主任みたいなやつ。
組織図の作成方法は病院によって違いますが、医事課長の責任は医事課全体、入院係長は入院全体、外来係長は外来全体と分かれます。急性期病棟主任と慢性期病棟主任とさらに分かれます。
総務課の仕事なのに医事課が担当していたり、看護部の仕事なのに検査科が担当しているみたいなパターンもあります。これは組織図を作っている院長や事務長の責任です。
たまに上司を動かすことができる部下がおります。いわゆる仕事ができる人です。組織において上司や同僚後輩はもちろん部署を跨いで仕事を進める人です。
そんな人はとても貴重なので伸ばして欲しいですが、病院のカラーと合わないみたいな理由で日陰を見ている人も多くおります。
クソみたいな指示しかできないなら上司なんて辞めちまえ
フワッとした指示しかできない上司がいます。
また何か質問してもフワッとした返事しかできない上司がいます。
仕事の中身を理解しないのでゴールの設定もできません。どのくらいのボリュームでどのくらいの人員でどのくらいの予算なのか。全くわかっていない上司も多いものです。
上司にも上司なりの勉強が必要ですね。