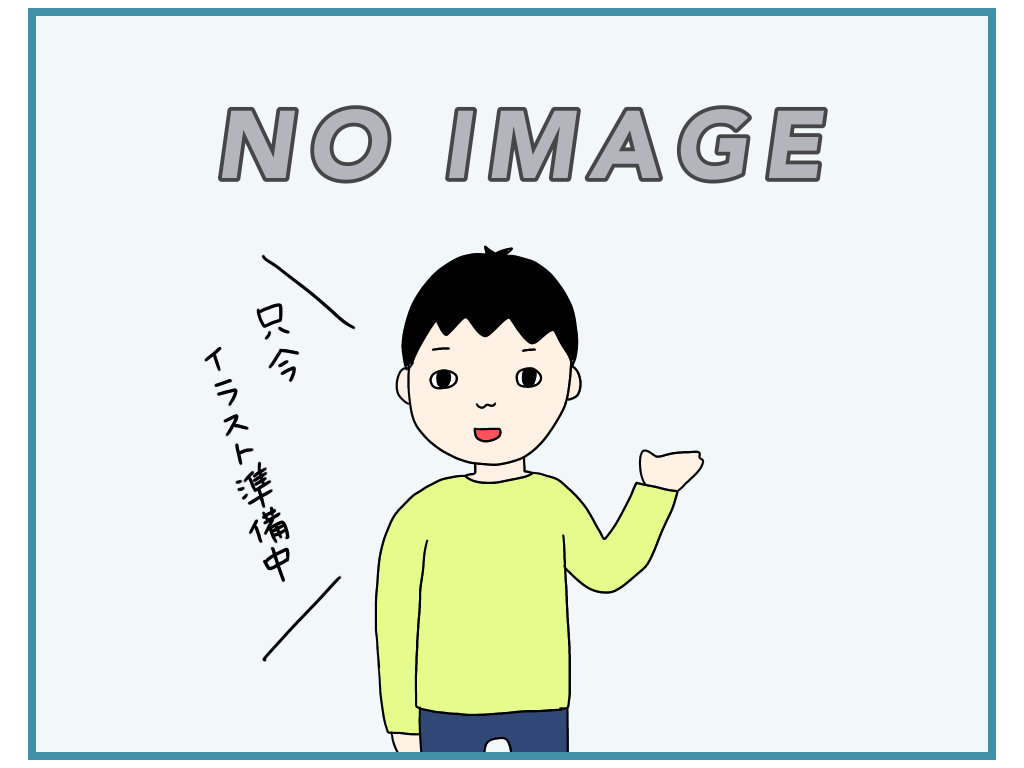出産無料のニュースが出てきましたね。SNSでも賛否両論の感じです。ぼくは病院の中で働いているので少し違う風景も見えてきます。
無料という言葉の響きは良いけれど、実際に無料になるのは患者さんの支払いだけ。医療機関にとっては費用は消えないし人手は減らない。むしろ物価も人件費も上がり負担は増しています。
今の出産育児一時金(50万円)では病院の出産費用には足りません。無痛分娩や深夜対応などがあると平気で60〜70万円は超える。それを「一律無料化」で吸収しようとしたらどこかで無理がでます。
患者負担もどこまでが無償化なのかまだ具体案は出ていません。
分娩を取り扱う施設は減っていて助産師も足りない状況です。制度の表面だけを見れば「いいことをしている」ように見える問題について書いてみたいと思います
病院の産婦人科はとても厳しい状況にあります
産婦人科はとても難しい病棟です。そもそも少子化で出産人数が減少しています。出産する母親が減っているし、出産するという選択をしない女性も増えております。
病院経営の視点では分娩が重なれば医師は寝る時間もない。しかも訴訟リスクは高い。今流行りのワークライフバランスが難しいので医師数も減少傾向。
無料にすれば出産件数が増えるんじゃないか、という期待もあります。
しかし、それ以上にお金の流れがどうなるかが問題です。医療機関にとっては産科って手間がかかる割に利益が出にくい診療科だし、人手も足りていませんからね。
診療報酬に含めるのか出産育児一時金を増額するのか
個人的に少子化問題は解決するべきだと思っています。
しかし、少子化の解決策が出産無償化だとは思いません。そして遅すぎますよね。せめて10年前には実施していなくてはいけない。
出産無償化がどこまでなのか。ここも問題です。「無償化」と言いつつ、結局オプションや個室料金は自己負担になるかもしれない。
診療報酬に含めても同じ。個室料金やら食費やら余計な出費は増えるでしょう。3割負担と高額療養費制度にするのも違うと思う。
個人的には余計なルールをこれ以上増やす必要はないと思う。診療報酬改定の度に複雑になり医事課の負担は増していくだけ。
問題の本質はどこにあるのか。政治的アピールなのでは。
無料化して需要だけ増えても対応できる病院がなくなって本末転倒なんじゃないかと思ったりする。
いまだってギリギリでやっている病院をいじめるようなルールになったら産婦人科を中止する病院も増えるでしょう。ここで集約化に成功して色々な問題が解決に進めば良いのかもしれませんが。
それに「出産が無料になったから子どもを産もう」という人がどれくらいいるのかは、正直よくわからない。少なくとも、ぼくの周りで聞く「子どもを産む」の悩みってもっと長期的で複雑です。
お金のことももちろんあるけど、保育園は?職場復帰は?実家の距離は?夫の家事スキルは?みたいな話の方がリアルだったりする。
とはいえ、出産費用が無料になるというのは大きなメッセージでした。ニュースにもなった。政治がちゃんと「子育て支援に本気ですよ」という姿勢を示すことには意味があると思う。
ぼく自身は、理屈よりも「産もうと思ってる人の背中をちょっと押せる政策」であれば、それだけで十分だと思っている。
本当の課題は、制度の整備だけじゃなくて、「安心して産める、育てられる」社会にしていくことなんじゃないかな。